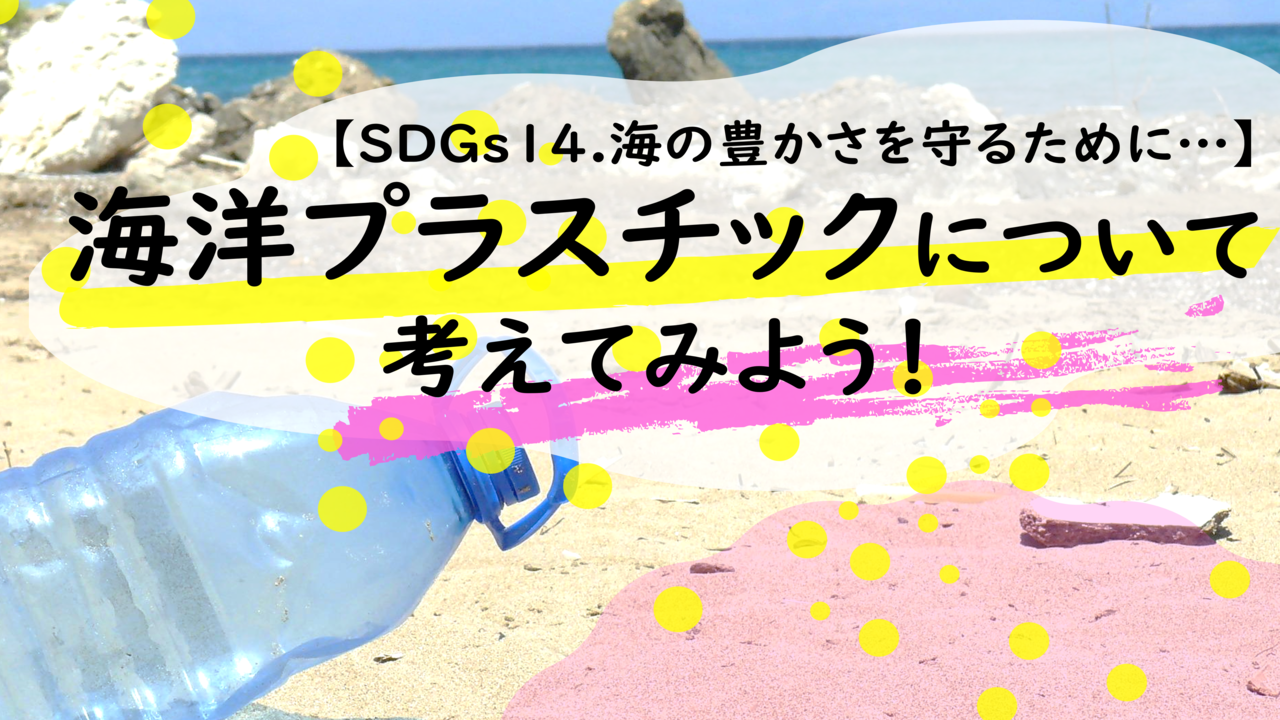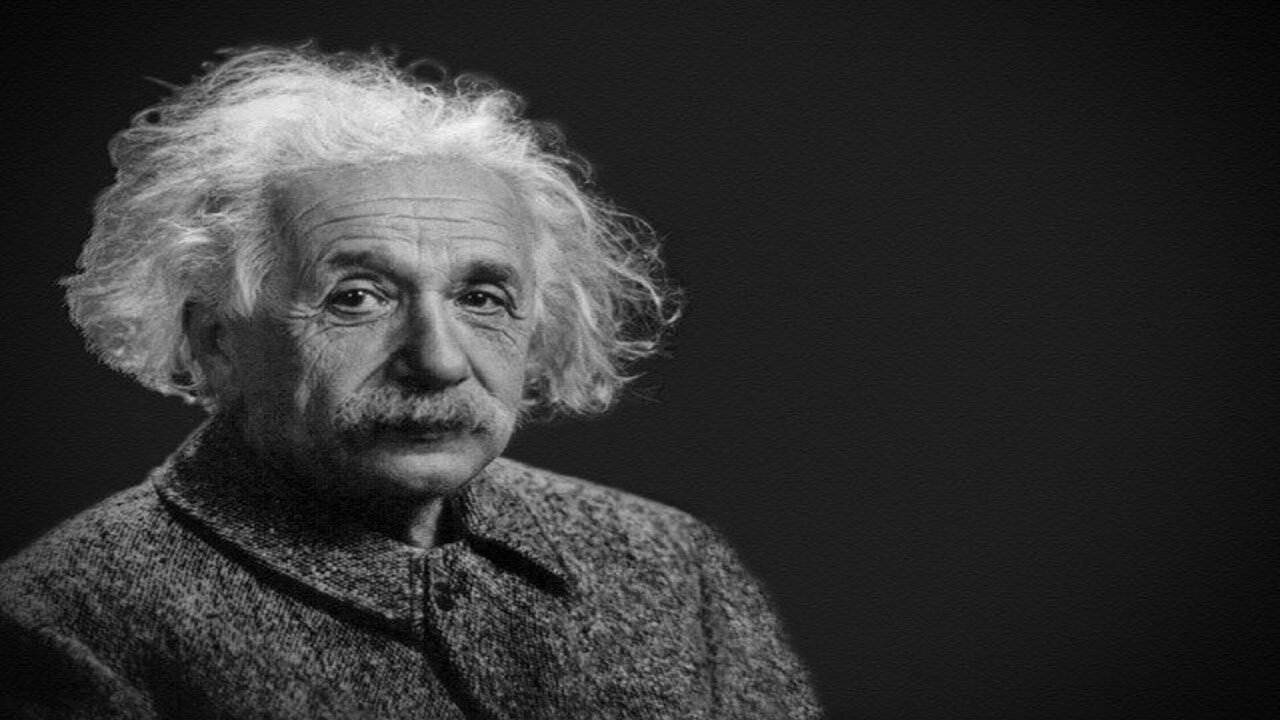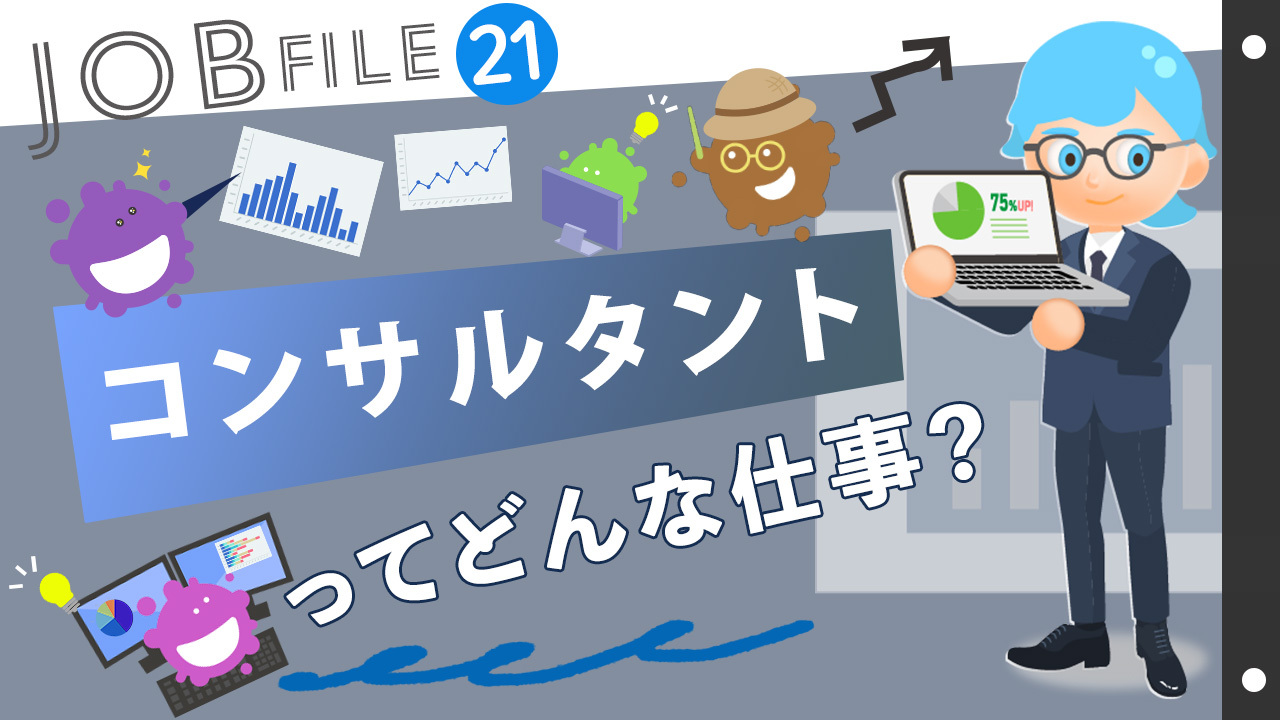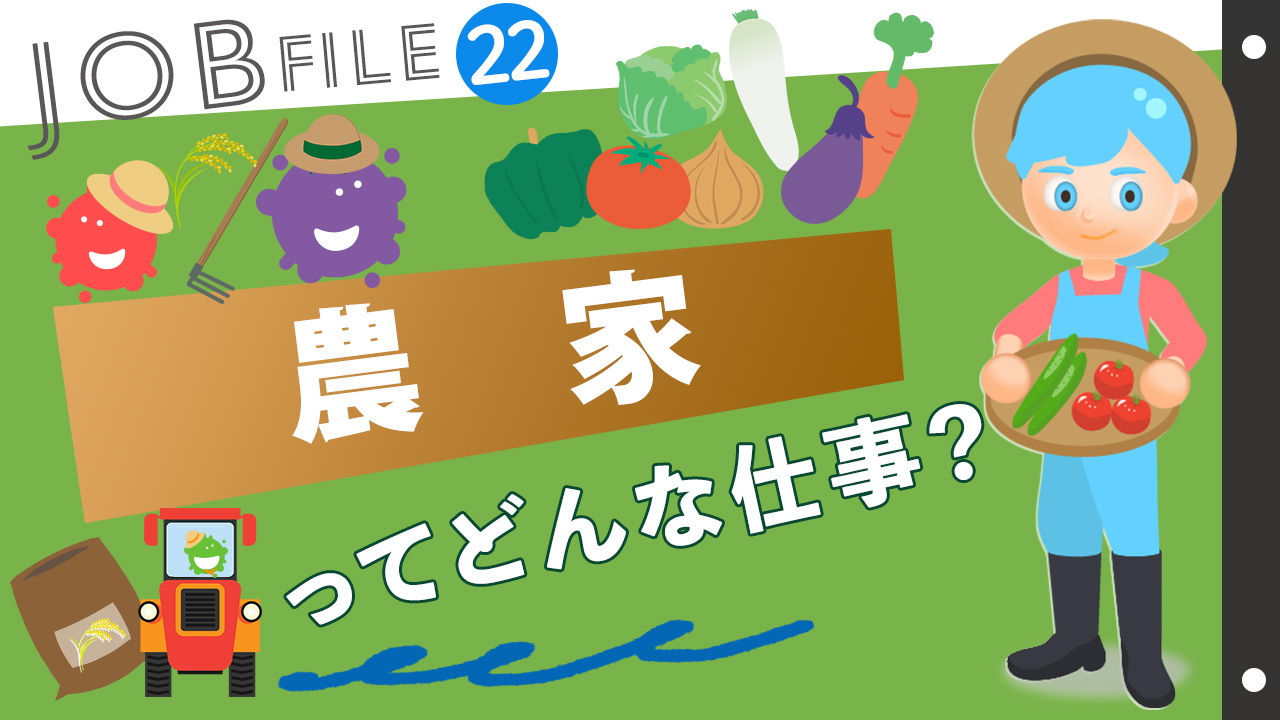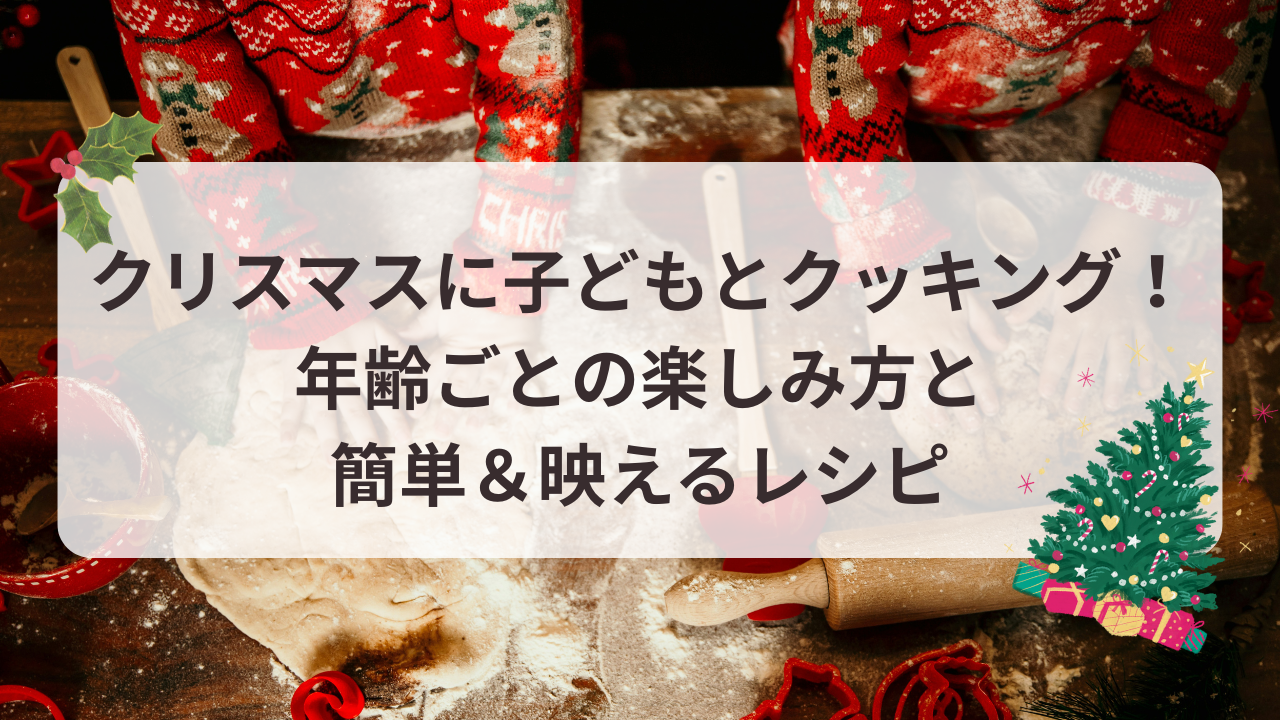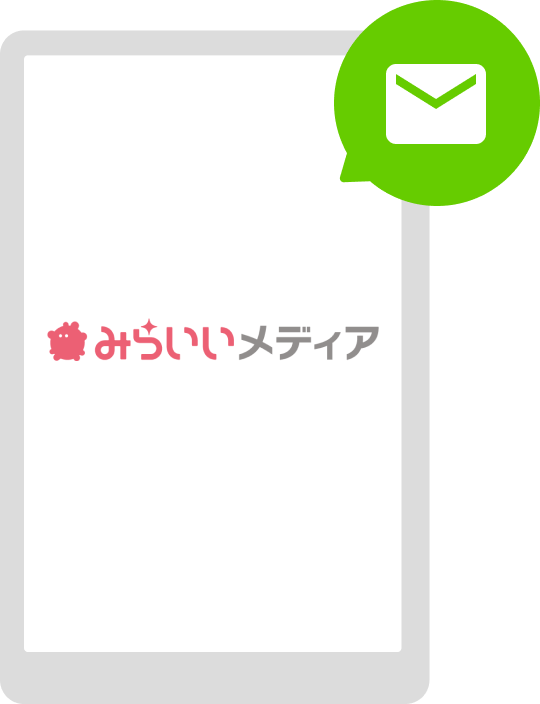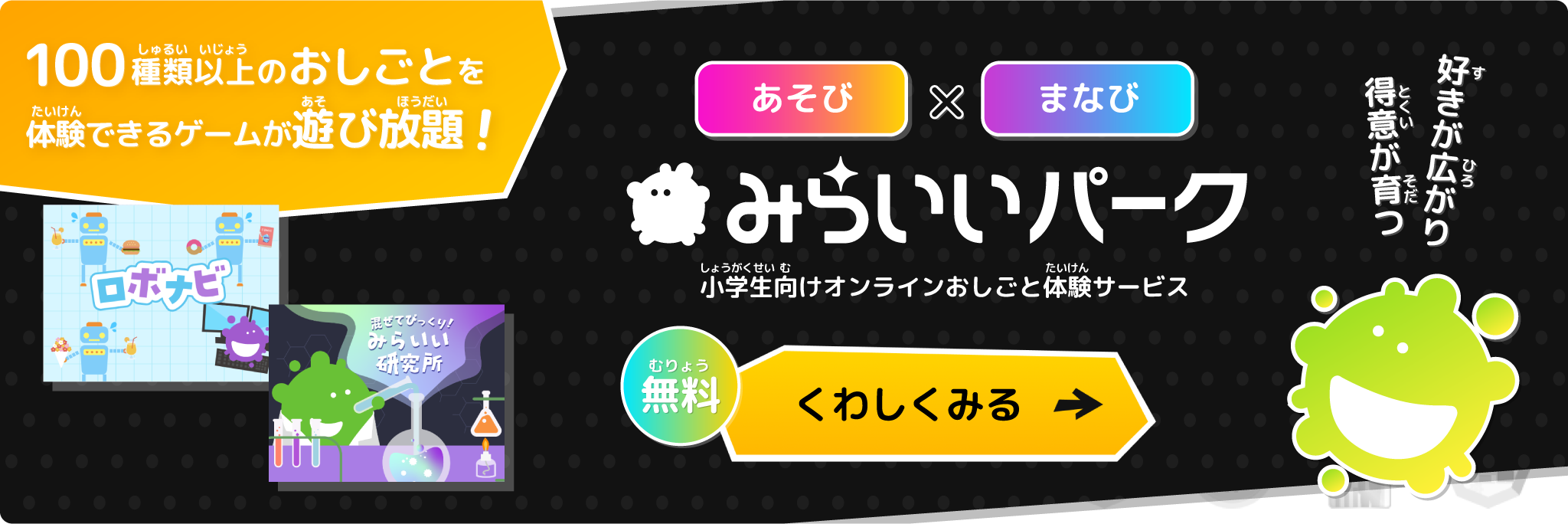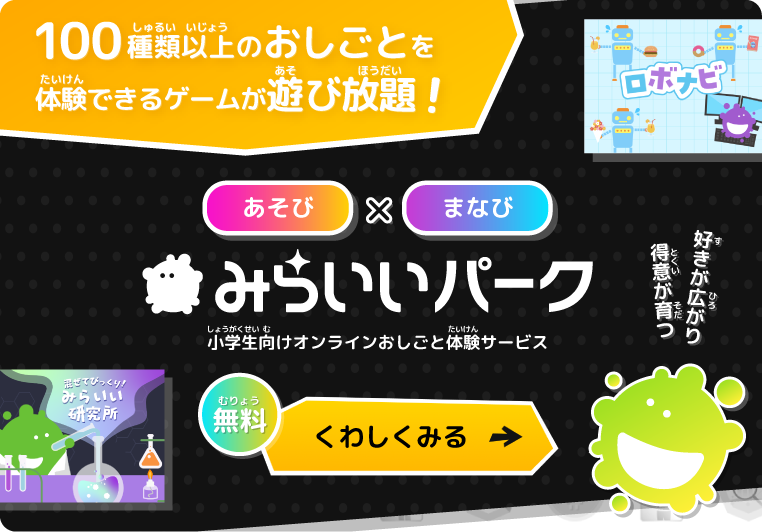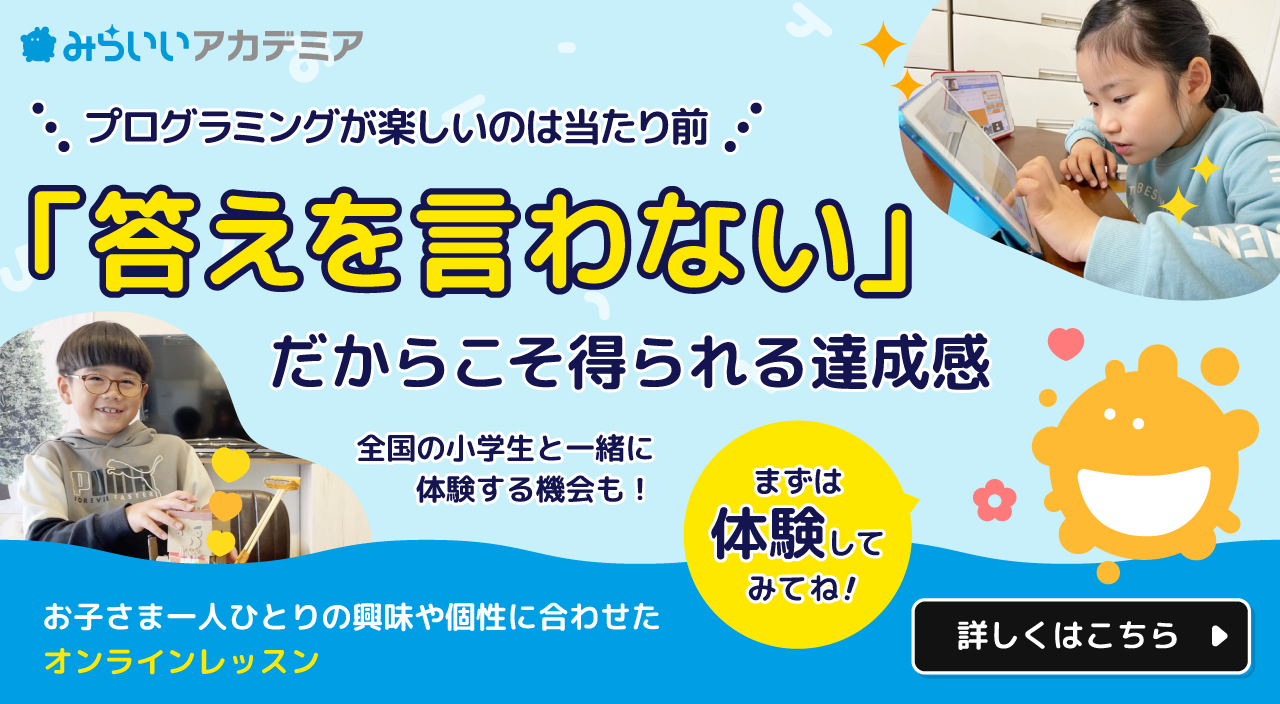この夏休みは怖いものを一つ克服!子どもの成長に繋がるヒントを紹介!

子どもに限らず、苦手なものや怖いことは大人になってもひとつやふたつはあるもの。
しかし、大人になるにつれ、苦手を克服することは難しくなります。
自分の子どもにも、苦手なものや怖いことはありませんか?もし、それを克服できたとしたら、きっと子どもの自信にも繋がっていくはずです。
そこで、子どものうちに、苦手をひとつ克服してみてはいかがでしょうか。苦手なものや怖いことを克服できれば、今後同じような場面にぶつかったとしても、自分の力で乗り越えていけるでしょう。
自分の時間をたくさん持てる夏休み。ぜひ苦手克服に取り組んでみましょう!
なぜ苦手なことや怖いものを克服することが子どもの成長に繋がるのか
子どものうちに苦手なことや怖いものを克服することが、なぜ子どもの成長に繋がるのでしょうか?
それは、「不安」や「恐怖」を抱いていると、普段不安や恐怖を抱かない対象にまでそれらを感じてしまうからです。不安や恐怖から葛藤状態に陥ってしまうことで、不安や恐怖に対し敏感になってしまうのです。
わかりやすい例で説明してみましょう。
ホラー映画を観た後で、お風呂に入ったとします。普段は普通に入れているのに、何となく後ろが怖かったり、窓が気になったりしませんか?
こういった現象を、心理学や脳科学では「一般化」と呼んでおり、認知行動療法の分野にて確認されています。
つまり、怖いものや苦手をそのままにしておくと一般化してしまい、克服するのに時間がかかってしまうというわけです。
大人になってもほかの対象にまで恐怖を感じてしまい、自身を辛くしてしまう。
したがって、子どものうちに怖いことや苦手を克服することは、これからの人生において恐怖や不安の対象を減らし、興味を持てることが増えること。結果的に、自分自身の成長に繋がっていくと考えられます。
参考:認知行動療法、鈴木伸一、熊野宏昭、坂野雄二「認知行動療法」1999年
子どもの「苦手」はどこから生まれるのか?
苦手克服について考える前に、ここで少し「苦手」のメカニズムについて触れておきましょう。自分の子どもに当てはまってはいないでしょうか?チェックしてみてください。
「自分の意識」が苦手を生み出しているケースもある
苦手なことや怖いものは、誰しもひとつはあるはず。しかし、それらは「自分の意識の問題である」ことがほとんどだそうです。
たとえば、「プール」が苦手な子どもがいるとしましょう。
子どもになぜそれが苦手だと思うのかを尋ねると、「水が怖いから」と答える子どもがいます。
苦手意識とは、特定のものや活動を「得意ではない」「好きではない」と感じる心理状態を指します。苦手意識は、過去の経験が作用して、自分自身への評価となって現れます。
「水が怖いからプールが嫌い」
プールが苦手な理由は、過去に水に対してネガティブな経験、つまり「強い水圧の水が急に顔にかかって怖かった」「興味本位で深いプールに入って溺れそうになった」などといった直接の経験があり、苦手と感じてしまうようになったと考えられます。
「水で怖い経験をした」→「水が苦手になった」→「プールが嫌い」というプロセスで、子どもは苦手意識ができていくというわけですね。
苦手意識が強いと失敗や挫折に対して不安を感じやすくなってしまい、さらに挑戦する意欲やモチベーションも低下してしまうでしょう。
ただし、苦手なことは、意識を変えることによって克服できる場合もあります。できないことをひとつずつかみ砕いていき、少しずつポジティブに意識を変えていくことが大切なのです。適切にサポートを行いながら子どもの自信を向上させていくことで、苦手意識が克服できる可能性もあります。
周りの言動が子どもに苦手意識を植えつけている
経験とは別に、周囲の言葉や態度で子どもに苦手意識を抱かせている場合もあるようです。
たとえば、親からの
- 「○○ちゃんはこの問題がすぐに解けたのに」とほかの子どもと比較する
- 「何でこの問題を解くのに〇〇分もかかったの!」とプレッシャーを与える
- 水が苦手な子どもを強制的にプールに入れる
といった言動があります。
いずれも、子どもを追いつめる言動になっているのが分かるでしょうか?
上記のような言動は、子どもに焦りや不安を植えつけ、ミスを生み、苦手意識を強める原因となっているのです。
さらに、もともと苦手意識がそれほど大きくなかったことも、ほかの子どもと比較されることで「自分はダメなんだ」「自分はこれが苦手なんだ」と認識してしまう子どももいます。
このように、周りの言動によって子どもが苦手意識を抱いてしまう可能性もあるのです。
苦手をどのように克服していくかを子どもに考えさせてみる

意識を少しずつ変えていくことで、苦手なことや怖いものを克服できるケースもあります。そこで、まずは、どうするのかを子どもに考えてもらいましょう。
子どもが考える機会を、親が奪ってはいけません。
「なぜ自分はこれが苦手なのだろう」と疑問を持つ、「どうやったら苦手をなくせるのか」と解決策を探すなど、子どもが考えるプロセスを大切にしてください。
ついアドバイスをしたくなるかもしれませんが、ここは黙って見守るようにしましょう。
また、子どもが自分で答えを出せなかったとしても、それを非難せず受けとめてあげましょう。何も考えずに答えが出ないのではなく、考えた末に答えが出せなかったというわけなので、考えたことを褒めてあげることも必要です。
たとえば、算数が苦手な場合、子どもは次のように考えるかもしれません。
「算数が苦手だ。なぜ苦手だと思うのか?」
「計算は得意なのに、文章問題が苦手だから。なぜなら文章の意味がよくわからないから」
このような場合は、文章の意味を読み解く読解力が必要になりますね。
「だから、もっと読書をすればよいのか。じゃあ夏休み、3日に1冊、本を読んでみよう」
という結論に至り、さっそくそれを実行に移せば、夏休みが終わるころには読解力が身に付き、文章問題に対しても以前よりは苦手意識がなくなっているかもしれませんね。
読書の効用や読解力については、以下の記事を参考にしてください。
読書初心者の子どもでも読みやすい!【学年別】おすすめの本を紹介 (miraii.jp)
子どもの読解力は落ちている?読解力が及ぼす影響とは (miraii.jp)
また、プールが苦手な場合。
「なぜ苦手なのか?水に顔をつけるのが怖いからだ」
「じゃあ、お風呂で少しずつ水に顔をつける練習をしてみよう」
というように、まずは子どもが自分自身で考える機会を持ち、自分で答えを導き出すことが苦手を克服するための第一歩となります。
苦手を克服する方法を親も一緒に考えてあげよう
子どもがどうしても自分で答えを導き出せなかった場合、ぜひ親も一緒になって考えてあげてください。
考えて、明確な答えを伝えるというよりは、子どもが考えることをサポートすると言った方がよいかもしれませんね。
引き続き、プールの例で解説しますが、「なぜプールが苦手なんだろう?」「じゃあ、水を怖がらなくなるにはどうすればいいだろう?」といったように、意見や考えを子どもが自分自身できちんと説明できるよう、やさしく導いてあげてください。
ガイドがつくことで、子どもも考えながら自分の意見をしっかりと口に出せるようになるはずです。
親だからといって、完璧な意見は必要ありません。「子どもと一緒に考える」姿勢やプロセスが大切なのです。
子どもが苦手を克服する際に親はどのようにサポートすればよいのか
克服する方法を子どもと一緒に考えたところで、子どもが実際に行動に移す場合、親はどのようにサポートすればよいのでしょうか。
過度に手出しをするのではなく、あくまでもサポートに徹することが大切だと言えます。
生活習慣の苦手は親や家族が手本になる

子どもにとっての苦手は、勉強や運動に限ったことではありません。
「野菜が苦手」「牛乳が苦手」といった生活習慣の苦手については、親をはじめ、ほかの家族が手本になる方法が有効です。
厚生労働省が推奨している、セルフ・エフィカシーを高める方法「モデリング」という方法があります。なお、セルフ・エフィカシーとは、ある行動をうまく行える「自信」を指します。
「モデリング」について解説すると、
モデルとなる人がしている行動を見て、「自分にもできそうだ」と思わせる
ことです。モデルは性別や年齢、生活状況など近い人が理想的とされているそう。
モデルは、苦手を克服するメリットやコツを、子どもに示すことが大切です。
たとえば、牛乳が苦手な弟に対して兄が「僕は牛乳を毎日飲んでいるから、身長が伸びたよ」という光景。実は、これも立派なモデリングと言えます。
牛乳を克服する方法を一緒に考えたうえで、親や周りの家族が積極的にモデルになってみましょう。「おいしそうに牛乳を飲んでいる姿を見せる」「牛乳をデザートに使って食べてみる」など、一緒に生活している親がモデルになることで、少しずつ牛乳嫌いを克服できるかもしれません。
参照元:セルフ・エフィカシーを高めるポイント (厚生労働省公式)
少し努力すれば達成できそうな目標を立て成功経験を積んでいく
前項目と同様、厚生労働省は、セルフ・エフィカシーを高めるポイントとして成功経験を積むことを推奨しています。そこでポイントとなるのが、少し努力すれば達成できそうな目標を立てることです。
目標を一気に大きく立ててしまう子どもも、中にはいるかもしれません。それでは、達成できなかった場合、再び自信をなくしてしまうでしょう。
時間がたくさんある夏休み。一日一日、少しずつ目標を立てて成功体験を積んでいくよう、サポートしてみましょう。
たとえば、「プール」に苦手意識を持っている子どもであれば、
最初は手ですくった水に1秒顔を付ける、次は3秒、次は5秒…と時間を長くしていき、手ですくった水への恐怖心が薄くなれば、洗面器の水に顔を付けてみる、次はお風呂に顔を付けてみる、と段階を踏んでレベルアップしていきましょう。
水に顔を付けることへの恐怖心がなくなれば、次は実際にプールに行って、プールそのものに慣れさせることから始める、といった具合です。
少しずつ成功体験を積んでいけば、体験と比例して子どもも自信がついていくでしょう。
具体的なところを提示して褒める
苦手意識の克服のためには、親がきちんと褒めることも大切です。褒めることで、さらに子どもが自信を持てるようになるからです。
ここでの大切なポイントが、子どもを褒めるときは表面的な事象だけではなく、具体的な内容を提示して褒めること。
たとえば、子どもが苦手な野菜を食べた場合。「すごいね」「えらいね」といった漠然とした言葉を並べても、あまり意味はありません。
「昨日は一口だったけど、今日はちゃんと3口まで食べられたね!」や「これだけ食べているから体も強くなっていくよ!」などのように、できるだけ具体的に褒めてあげると、子どもはちゃんと自分のことを見てくれているんだと嬉しくなり、意欲を持って苦手克服に取り組んでいけるようになるでしょう。
たくさんよいところを見つけて、褒めてあげてください。
褒め方のコツは、以下の記事でも詳しく解説しています。
知っておきたい! 子どものやる気をグングン伸ばす「言葉がけ」とは! (miraii.jp)
自己肯定感をグッと高める! 子どもへの接し方とは? (miraii.jp)
小学生の自己肯定感を高める方法とは? 子どもと今すぐ始められること! (miraii.jp)
苦手を克服できればそれは子どもの自信に繋がっていく

苦手を克服できれば、それはどんな小さなことでも子どもの自信として積み重なっていくはず。
そうすると、よい結果を出せるようになり、「苦手なこと」は得意なことに。「苦手なこと」を克服できた嬉しさ、成功体験を繰り返していくうちに楽しさも見出せるようになり、好きなことへと変わっていくかもしれません。
また、「自分だってがんばればできるんだ」という自己肯定感も芽生えます。
どんな小さなことでも「苦手なもの」や「怖いこと」を乗り越えられたら、たとえ今後同じような壁にぶつかったとしても、自身の力で乗り越えていけるようになるのではないでしょうか。
まず自分自身で考えることが苦手克服への第一歩となる
苦手を克服するためには、子どもが自分自身で方法を考えることが大切です。
悩んだ時や困った時は、まず考えてみる。
学力や知識を習得する前に、まずは自分で考えるという習慣を身に付ける方が、これから生きていくうえで大きな力となります。
答えが出なかったとしても、子どもが自分で考えたことを褒めてあげてください。一緒に考える場合でも、親は過度に口出しするのではなく、サポートする立場で支えてあげましょう。
自分の時間がたくさんある夏休み。
この機会に、苦手克服に少しずつ取り組んでみてはどうでしょうか。苦手をひとつでも克服できれば、きっと自信も持てるようになるはずです。
夏休みには「生きる力」も育んでみてはいかがでしょうか?
夏休みは小学生の「生きる力」を育むチャンス! (miraii.jp)
絵が苦手な子どもには、以下の記事がおすすめです!
小学生が上手に絵を描くコツとは?親のサポートによって上達度は変わる! (miraii.jp)







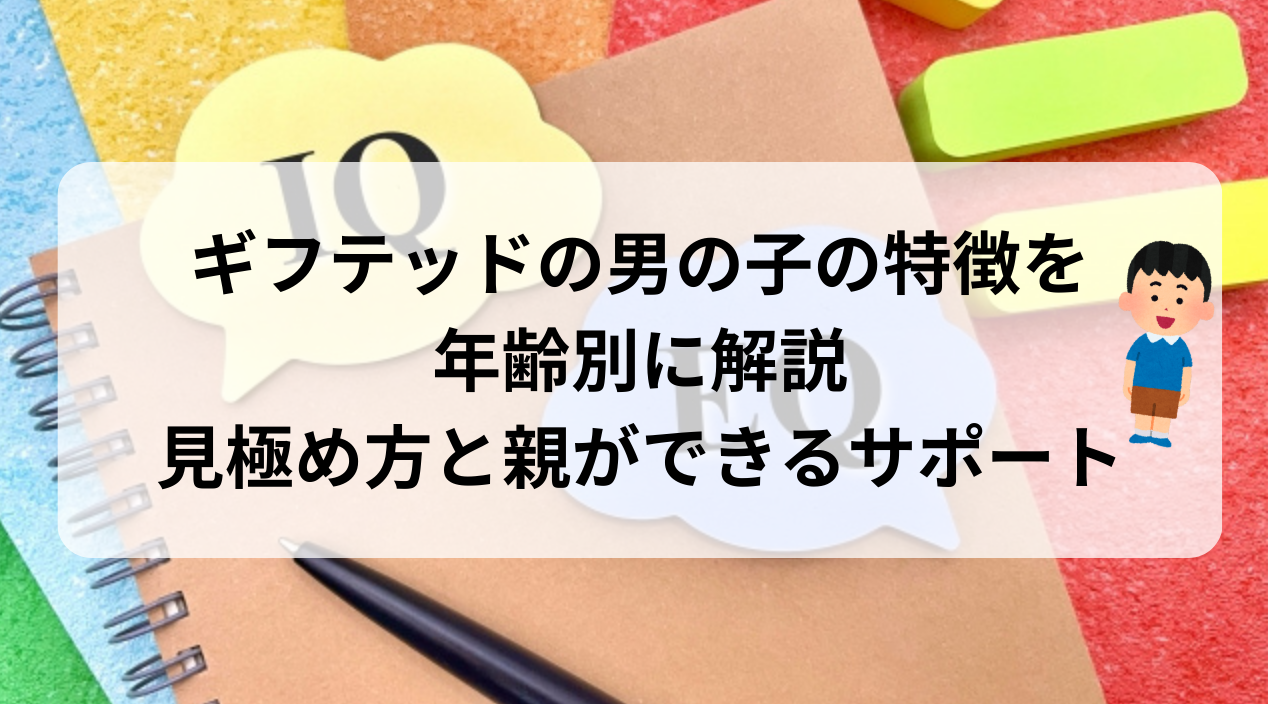



%20(1).jpg)